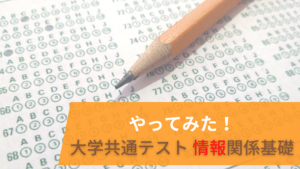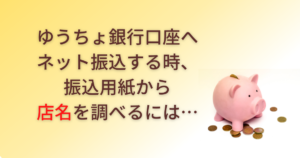本日、2023年9月6日で、胆振東部地震から5年になります。
このブログ記事は昨年新規作成したものですが、1年ごとに振り返りを追記していこうと思います。
今年の夏は猛暑でした。
これを書いている9月6日、千歳の最高気温は28度くらい。
台風の影響で蒸し暑く、日中はクーラーをつけています。
そんな中迎えた9月6日。
5年前の9月6日は、地震発生後まもなくしてから8日まで、電気が使えない状態になりました。
今、あの震度6弱を迎えたらどんな状況になっているだろう…。
お昼の全国ニュースで、胆振東部地震発生から5年が取り上げられていました。
北海道新聞WEBサイトでは、数日前から、地震の振り返りと現状についての特集がありました。
わが家の備えについて。
昨年のこの日に備えが足りてないな…とダンナと話合い、ペットボトルの飲料水2本と、トイレ脇に水道水入りのペットボトル2本、常備するようになりました。
玄関脇に、防災グッズセットが置いてあります。
5年前の震災直後に購入したローソク・懐中電灯・防災ラジオなどと合わせて、数は揃ってきたように思います。
そして、気持ち的な備えはどうだろう。
あの時まだ抱っこ紐で抱っこしていた子どもは、小学校1年生になりました。
子ども連れでの避難生活というのが、一番の心配です。
あの時苦労した、子どもを抱っこしての徒歩での買い物はしなくてすむかも。
でもたぶん、怖くて泣くのをなだめるとか、別のケアが必要になるんだろうな…と想像します。
避難所に行かなければならない状況になったらどうだろう…。
そもそも、避難所、小学校でいいのかな…。
普段考えないことを、この時期にまたしっかりと考えなくちゃな、と思います。
来年振り返ったとき「去年はこれをやったな」と思いだせるように、少なくとも防災グッズの点検だけはしようと思います。
今年は8月から9月にかけて、慌ただしく過ごしています。
お仕事を立て続けに頂いている事が大きいのですが、その他にも、子どもの保育園行事が続いたり、8月はお盆だったこともあり、家族の用事も重なりました。
テレビはもちろんSNSもほったらかし。
辛うじて、大きなニュースだけはダイジェスト版を何かで見て把握しているという感じです。
*
でもやっぱり。
このニュースだけはじっと見てしまいます。
「9月6日、北海道胆振東部地震から4年となるこの日…」
そう、ここ千歳で、わたしは胆振東部地震を経験しました。
*
9月6日の地震発生から8日まで、電気が使えない状態になりました。
ガスと水道が使えたのは幸いでした。
※集合住宅の方は水道は使えなかったと、後に聞きました。
自分用の車が無かったわたしは、抱っこひもで子どもを抱っこしながらお店を2~3つ見に行った記憶があります。
パンやおにぎり、葉物野菜、牛乳などの生鮮食品、お米はどこのお店にも無かったです。
電池やろうそくも、ありませんでした。
ガソリンスタンドに長蛇の列が出来ていました。
*
子ども連れで大きな災害を経験したのは、これが初めてでした。
普段でも抱っこ紐で子どもを連れながら移動するのはしんどいのですが、災害時はプラス緊張感で倍疲れた気がします。
しかも、お店に行っても欲しいものが買えなかったので、帰路はかなり疲れてしまっていました。
*
その買い物歩きの途中、80歳くらいのおばあちゃんと信号待ちで立ち話しました。
「戦争も経験したけどねぇ、この地震も大変だよねぇ。」
と、けっこう離れたところにあるスーパーに歩いて向かうとか。
年の割にはしゃきしゃきと歩いていくおばあちゃんを少し見送り、わたしもドラッグストアに向かいました。
*
わたしはこの数週間後、パートの職を得て働き始めました。
結婚&出産後、久々の社会復帰でした。
そこでこの地震の当時のことをいろいろ聞きました。
同じ千歳市内でも、電気が使えるようになった日が1日程度違う地域があったこと。
病院など、インフラがある地域は早く電気が復活したこと。
同じように不安を抱えていたママと、あの時どうやって過ごしていたかを話しました。
「会話」の力。
今まだ続いているコロナ禍でも感じますが、人と話すことは、大きな力なんだな…と思います。
ネット記事を読んでも、SNS閲覧でも、情報は得られます。
でも、お隣さんや普段から行っている子育て支援施設など、身近な人と交換する情報が何より強力だと感じます。
「不安な時こそ話をしよう」。
地震の教訓として、コロナの教訓として。
子どもや身近な人に、伝えていきたいな、と思っています。